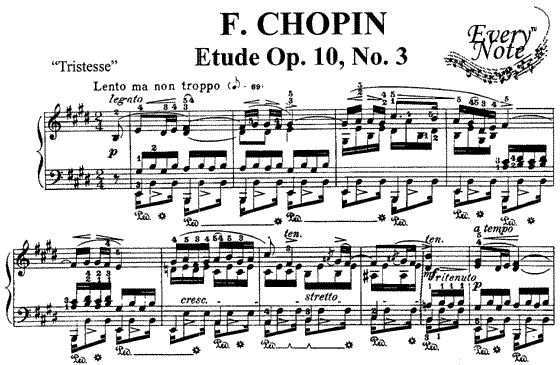
十一月の土曜日の空気は、ベッドで丸くなっていても冷たかった。時刻は午後四時を少し回ったところ。夜型の生活を送っているユウジにとって、土曜日の夕方に目覚めることは普通だった。今夜は大学の友人と合コンの予定がはいっていたので、あまりのんびりしている時間はない。それでもベッドの上で芋虫になってしまうのは、彼の心が蝶になって外へはばたくことを拒んでいるからだろう。合コンというイベントを甘い蜜と感じられたのは、とうに昔のことだった。
ずぶずぶとベッドから這い出てパソコンの机に座ると、タバコに火をつけながら音楽プレイヤーを開いた。一日の最初にすることは、音楽を聞きながらタバコを吸うこと。五百曲以上あるリストの中には、ポップスからジャズ、クラシックまで、さまざまなジャンルがある。いつも適当にスクロールしながら、夜空の一番星を見つけるような偶然で一曲を選ぶ。今日は何となく、目を閉じたまま画面のどこかをクリックする手法に変えた。そんななかで流れた曲は、ショパンの別れの曲だった。
「……」
ユウジはすぐに停止ボタンを押して、あたりさわりのないJポップを流した。ショパンは決して嫌いではない。だが、この曲を聞くことはつらかった。別れの曲は、まえに付き合っていたサナエが大好きな曲だった。
サナエとは、約一年前に別れた。彼女がさよならを告げた理由は、「他に好きな人ができたの」というなんともありきたりなもので、そんな気配にまったく気づいていなかったユウジはひどくショックだった。本当なら別れたくなかった。ただ、部屋で大泣きをしながらあやまる彼女を前にして、彼は抵抗する言葉を見失ってしまった。
「まぁ、仕方ないよ。サナエの気持ちが決めたことなんだから。俺は大丈夫だから、もうそんなに泣かないでよ」
と強がってみせ、部屋の隅に置いていた電子ピアノを取り出してショパンの別れの曲を弾いた。気持ちに余裕があったわけではない。彼女の涙をまえにして、嫌だと言うこともできず、どうしたらいいのか分からなかったのだ。サナエの罪悪感が痛いほど伝わってきて、少しでも彼女の苦痛をやわらげたいという思いもあったかもしれない。ただ、いま思い返せばあんな場面で別れの曲なんかを弾いた自分がひどく滑稽だった。
タバコを吸い終えると、服を着替え、髪を整えた。ささやかに香水をつけ、戦う準備をそれなりにするが、合コンで素敵な出会いを見つけようとか、新しい恋をしようなどという気持ちはない。彼女と別れてから複数の女の子と関係をもってきたが、そのほとんどが一夜限りのパートナーで、ただ一人ぼっちの寂しさを埋める作業でしかなかった。
今日もまた、カラカラに乾いた心を潤おすために街へ出る。サナエではない水を求める期待と憂鬱のはざまでゆれながら。
夜の街は、週末ということもあって、浮き上がるように歩く人々であふれていた。小雨を浴びたネオンの血がギラギラと騒いでいる。
ユウジが駅前の居酒屋に着いたころには、彼以外のメンバはすでに揃っていた。遅いぞ、という友人たちの非難を浴びながら、向かいの席に座る女の子たちへ目で挨拶をする。彼のギアはローからミドルへ上がっていた。
今夜の相手は、市内の看護大学に通う女子大生らしい。四対四。さっと目配せをしたなかで、彼のタイプの女性が一人だけいた。小柄でほっそりとしているが、胸は大きく、リスのような小動物の顔をしている。他の三人も悪くはないが、容姿だけなら彼女が当確だ。別に彼女を探しているわけではないので、内面まで考慮する必要はない。
「ハルカさんは、どうして看護師になろうと思ったの?」
一回目の席替えで目当ての女の子と話す機会にめぐまれた。彼女の名前はハルカ。二十一歳。国会議員ではないのでプロフィールを詐称していても何の問題もないし、興味もない。彼女と和むための会話を機械的に行うだけだ。
「私って四人家族なんだけど、私以外みんな気管支が弱くて、病院にお世話になっていたの。それで看病の手伝いなんかをしていくうちに、だんだんと興味がわいてきて、この仕事につきたいって思ったんだ。私の弟なんかぜんそくがひどくってさ、あれは小学生のときだったかなあ。二人で留守番していたときに弟の発作が出てね……」
ハルカは、こちらが一つの質問をすれば、五つの話を展開する女の子だった。物静かな人も嫌いではないが、これから先のことを考えると口数の多いほうがずっとやりやすいことは確かだ。僕は黙って聞き役に徹して、ときおり彼女の共感を得られるようなレスポンスをはさんだ。
「ユウジくんの趣味はなあに?」
二人の間で交わされる酒は大した量ではなかったが、彼女の口調はいい加減に巻いた毛糸の束みたいにゆるくなっていた。彼女は酔いやすいタイプなのだろう。酒に強いユウジは、女の子よりも先に意識レベルを下げたことはなかった。
「あえて言うならピアノかな。自宅に電子ピアノがあって、クラシックだったらたいていの曲は弾けるよ」
「へえ、すごい。男の子でピアノを弾けるなんて、格好いいよね。聞いてみたいなあ」
「いいよ。今度、うちに遊びにきてくれたら聞かせてあげる」
「やった。約束だからね」
お互いの趣味や将来の展望、他愛もない話で盛り上がり、彼女ともだいぶ打ちとけていた。ハルカにしても彼に好意をもっているようだ。店内の薄暗い証明のなかで、彼女の瞳はたっぷりと熟れたりんごのようにみずみずしく輝いている。
しばらく、居酒屋で会話を楽しんだあと、八人は連れ立って近くのカラオケで二次会をした。カラオケという場所はあまり好きではなかったが、マイクを向けられたら歌わないわけにはいかない。目的を達成するためには、少しくらいの我慢は必要だ。人生と同じだろう。
終電の時刻が近づいてきたのに合わせて、合コンは解散となった。それぞれ一様に満足な顔をしていたので、これから男女のドラマが枝分かれしていくのかもしれない。
ハルカとは帰りの電車が同じだったので、駅のホームで上手い具合に二人きりになった。プラットホーム内のベンチはほとんどが空席だったが、二人は冬の冷たい空気を理由にして、肩を寄せ合って座っていた。こんな状況で女の子にかける言葉は一つしかない。
「良かったら、これから家に来ない?」
「うん……、いいよ」
酔いが回って、少し鼻にかかった声に、ユウジの鼓動は音を立てて鳴りはじめた。彼女との間にあった壁は崩れ、残る障害は全身を覆っている衣服だけだった。はじめての女の子と性行為をすることが確定したときに感じるときめきは、かけがえのないものだと思う。
もったいぶりながら走る電車に揺られ、二人は駅からユウジのマンションへまっすぐ向かった。部屋に入ると、彼らはテーブルを囲んで話すこともせずに、立ったままキスを交わした。彼女の鞄が床に落ち、二人の身体もそのままベッドへ落ちていく。ユウジと同じようにハルカも待ち遠しかったようだ。
服も下着も外したハルカはとても魅力的なプロポーションをしていた。生まれたばかりの子猫に触れるように、慎重な手つきで、彼女のひとつひとつに刺激をあたえていく。頭の上からつま先まで、お互いの肌の感触を充分に確かめあったあと、ユウジは彼女のなかへ入ろうとした。
部屋の白い明かりと白いシーツにはさまれて、ハルカの頬が紅く映えている。こうして、いろんな人と落ちていくことで、サナエとの思い出を少しずつ消しているのかもしれない。
ふっ、とそんなことが頭をよぎったとき、ユウジの瞳からハルカの存在は消えていた。下半身の熱がまたたく間に冷めていく。
「……どうかした?」
急に動きが止まった彼を、ハルカは不思議そうに見上げた。ユウジは、何でもないよ、と言いいながら慌てて彼女の下腹部に自分のものを添える。まさか、君が誰だか分からなくなった、なんて言えるはずもない。彼の性器もこの程度のことでしおれることはなかった。
二人の身体は結合され、車のアクセルを踏み込むように徐々に加速していく。ベッドがぎしぎしと悲鳴を上げ、同じようにハルカの口からも切なそうな声が漏れた。ユウジの腰も快楽に溺れる。二人は確かにつながっている。しかし、彼の身体がハルカの奥へ入るたびに、自分の心の傷をえぐるような感覚におそわれるのは何故だろう。自分が本当に求めているのは、ハルカではなくてサナエだからか。こんなことをしても何の意味もないと、頭の中のもう一人が告げている。自分勝手の罪悪感が、性欲のはざまで波打つ。たぶん、ハルカとサナエの二人に対して……。
欲望が果てて行為が終わると、ベッドにうつぶせになって目を閉じた。長距離マラソンを終えたランナーみたいに、全身はくたくただ。自分からはやく終わりたい、なんて思ったことは二十一年の人生のなかではじめてだった。
枕元に転がっていたリモコンをつかんで、部屋の灯りを落とした。すっかり老化している蛍光灯の光でさえも、今の自分には眩しすぎる。呼吸が整って辺りが静かになると、何だか無性に悲しくなった。
「ねえ、おいでよ」
声に誘われて隣を見ると、ハルカが半身の体勢で左手を広げていた。口元に浮かんだ微笑みは、まるで彼の気持ちを察しているかのようにあたたかだ。
ねえ、おいでよ。始めてのセックスの後に、こんなことを言われたことはなかった。彼女の胸の中にできた空間へ本能のままに吸い込まれた。汗ばんだ背中に彼女の手のひらが添えられる。人を抱きしめること、抱きしめられることは、こんなに安心するものなのか。自分でも気づかないうちに、ユウジの目には涙がたまっていた。デパートで迷子になって母親と再会できたような、自分は一人ではないとあらためて気づかされるときに流す涙に似ていた。
狭いシングルベッドの上で彼らは抱き合い、互いのぬくもりを共有しながら静かに眠りについた。
目が覚めると、いつもとは違う夢の内容に彼は戸惑った。
夢の中にはサナエがいて、新しい恋人と楽しそうに街を歩いていた。週に三回は彼女の夢を見るので、そのことは不思議ではない。ただ、普段はサナエの姿をひとりで見ているのだが、今回はとなりにハルカがいた。彼女は自分にとって束の間のパートナーのはずなのに……。
左手でハルカが寝ていた空間を探ってみるが、皺になったシーツのごわごわとした感触しかなかった。部屋を見回しても彼女とともにバックも消えていたので、すでに帰宅したのだろう。全身が凍えるように寒いのは、自分が下着だけの格好だからだ。これが、当たり前の現実だろう。昨日、会ったばかりの女の子を夢の中のゲストにするほうがどうかしている。
「あ、ようやく起きたね。おはよう!」
ふいに玄関のドアが開けられ、ハルカが勢いよく入ってきた。手にはコンビニの袋をぶら下げており、化粧もすでに直されていた。
「帰ったんじゃなかったの?」
予想外の再来におどろいて、彼は服を着るのも忘れてたずねた。
「うん、はじめはそう思ってたんだけど。ユウジくんを一人で残しておくのが、なんだか悪い気がしてね。朝ごはん買ってきたから一緒に食べよ」
彼女が買ってきたサンドイッチを食べながら、今のことばの意味について考える。どうして自分を一人にしておくことが悪いと思ったのだろう。昨夜の自分は、初対面の女の子に心配をされるほど寂しそうに見えたのか。
太陽の純粋な光が窓から差し込み、暗闇が室内から逃げ出そうとしている。ユウジのなかの暗闇も我慢ができなくなったように、胸からのどを通って脱出した。心の闇は酸素に触れると言葉になる特性をもっている。
「昨夜、ハルカを抱いているとき、僕は前の彼女のことを思い出していたんだ。別れたのは一年前なのに、まだ忘れられないんだ。情けない男だろ」
苦笑いを噛み殺しながら自嘲すると、ハルカは少し考えるような顔をして言った。
「そっか……、でも何となくそんな気はしていたよ。あぁ、この人はいま私じゃなくて別の人を見ているんだろうなって。昔の恋を忘れられないのは誰だってあるし、裏返せばそれだけ真剣に恋愛をしていたってことだと思うから、そんなに自分を卑下することはないんじゃないかな」
てっきり彼女からは非難されると思っていたので、素直におどろくとともに、自分のやるせなさは逆に強くなった。どうして、自分はいままで他人の優しさに目を向けようとしなかったのだろう……。ふと、サナエが別れを告げたときの言葉を思い出した。
「ユウジは、自分が考えてることとか、ぜんぜん言ってくれなかったよね」
そのときは、そんなことはないと強く否定したが、いま振り返ると心の一部では図星だと感じているところがあった。そして、サナエの指摘はどうやら的を射ていたようだ。彼女と別れてから関係をもった人たちとも、自分は身体よりも大事な部分を求めようとはしなかった。ただ、めんどうだからの一言で片付けていたが、本当は他人の心へ踏み込むことも怖れるくらい臆病な人間なのだ。
「あ、電話だ。ちょっとごめんね」
ユウジが黙ってうつむいていると、ハルカは携帯電話を持ってわざわざ玄関の方まで歩いていった。部屋の間取りはワンルームだったが、彼女が何を話しているのかは分からない。ただ、表情がどこか強ばってみえたので、電話の相手は家族や友人というわけではなさそうだった。
「電話、誰からだったの?」
できるだけ押し付けがましくならないように、彼女との距離感を意識しながらたずねた。すると、彼女はどこかばつの悪い顔で照れくさそうにいった。
「半年前に別れた彼氏からだった。ときどき、こうやって不意打ちに連絡がくるんだけど、いまだに声を作って話しちゃうのよね。だから、私もユウジくんと同じ。情けない女なの」
いたずらがばれた子供のように肩をすくめるハルカがおかしくて、思わず吹き出した。そして、これまでの彼女の言動が妙に心に響いた理由も分かった気がする。ハルカも自分と同じように過去の恋愛をポケットに隠し持っていたのだ。おかしな言い方をすれば二人は戦友だった。
「彼のこと、まだ好きなんだね」
君も戦場にいるんだね。共通の趣味をもつ友達を見つけたような調子の良さで言うと、彼女は少しだけ顔を崩した。
「うん……、実はそれもよく分からないんだ。私が彼のことを嫌いになるまえに向こうから別れを切り出されたから、ただ引きずっているだけなのかなって。彼はもう新しい恋人がいて、私のことは友達の一人としてみているけど、それが何か悔しいだけなのかもしれないし」
よく分かんないよね、と最後に付け加えてハルカは天井を見上げた。今の彼女のことばを自分に置き換えて考えてみると、不思議と視線は天井に向かった。自分も、まだサナエのことが好きなんだろうか。ただ失恋を認める勇気がなくて、もう終わったはずの恋にしがみついているだけなんじゃないか。純白の天井は何も語りはしなかったが、天井が白いということだけで、何か充分な気がした。
「そうだ、ユウジくんってピアノ弾けるんでしょ。せっかくだから、何か聞かせてよ」
「いいよ。居酒屋で約束したしね。クラシックで、何か好きな曲はある?」
「んー、クラシックはあまり知らないんだけど、ひとつだけ大好きな曲があるんだ。ショパンの別れの曲」
その曲名を聞いたとき、ユウジの呼吸は一瞬止まった。サナエが大好きだった、別れの曲。最後に彼女のまえで演奏してから一度も弾いていないし、この曲だけはなるべく関わらないように生きてきた。
「あ、別れの曲はレパートリーに入ってなかったかな。別に他の曲でもいいよ」
顔色を失ったユウジの反応をみて何かを察したのか、ハルカは慌てていった。しかし、彼の決意はすでに固まっていた。
「いや……、僕もこの曲は大好きだよ。久しぶりだからうまく弾けないかもしれないけど、いま、ハルカにいちばん聞かせたい曲かもしれない」
部屋の隅でほこりをかぶっていた電子ピアノを取り出すと、鍵盤に手を沿え、深呼吸を二回した。譜面は指が勝手に覚えている。なんども、なんども、サナエのために弾いた曲だ。あれからもう一年になるのか……。人差し指が、最初のシの音を押さえたとき、ユウジの意識はサナエと出会ったころにまでさかのぼった。
単音から始まったメロディーは、サナエとの思い出を表現するように、さまざまな和音の組み合わせで奏でられていく。一小節ごとではなく、一音ごと。その一瞬の音がすべて、彼女と過ごしたかけがえのない時間を刻んでいた。ユウジは鍵盤を歌わせながら、二人で歩んだ軌跡をたどっていた。これが、彼の心の中から、自分勝手に歪ませてしまったサナエのイメージを追い出すための最後のデートだった。
曲が終盤になるにつれて、激しく叫んでいた音色は落ち着きをとりもどし、やがて静寂がおとずれる。サナエにさよならを告げるため、メロディーはゆっくりと流れていった。最後の一小節を弾きながら、ユウジは心の中で言った。
さようなら。いままで、ありがとう。
最後にミの音を響かせて、別れの曲は終わった。彼女との思い出を五分にも満たない曲のなかに凝縮したせいか、鍵盤から手を離すと、長い旅を終えたような達成感と切なさがあった。しかし、いまはこれで終わりではない。新しい旅がまたこれから始まるんだと思うと、とても清々しい気持ちだった。
パチパチパチ、と背中越しに拍手の音が聞こえ、ユウジはハルカのほうへ向き直った。彼女は手を叩きながら、少し涙ぐんでいた。
「ピアノ、すごく上手だね。なんだか……、感動しちゃった」
別れの曲を聞きながら、彼女は彼女なりに思い出を整理したのかもしれない。ユウジの目にも涙があふれ、気がつけば二人で泣いていた。いままでの二人に何があったのか、具体的なことはまったく分からなくても、彼らはお互いの涙の意味は知っているようだった。
別れの曲の演奏時間よりもさらに長い間泣き続けると、彼らは自分たちの顔を見合わせて笑っていた。目も鼻も真っ赤で、どちらもひどい顔だったからだ。ティッシュで顔をふき取りながら、ハルカが言った。
「ねえ、いまから昨夜のセックスをやり直そうか。今度こそ、二人だけでしようよ」
それも素敵なことだな、と思ったが、ユウジはことわった。
「いや、それよりも、街に出てデートをしよう。いまからが本当の始まりだから、ひとつずつ、順番に楽しもう」
そして、二人はぐちゃぐちゃになった顔を綺麗にして、十一月の澄んだ空気の中へ飛び出した。気の早い街並みは、もうクリスマスのイルミネーションで飾り付けられている。そんな浮き足立った街の中を、彼らは手をつないで跳ねるように歩いていった。キスよりも、セックスよりも、彼女と手をつなぐことのほうがユウジにとっては特別なことだった。
「ねえ、私だけ昨日と同じ格好なんて嫌だから、新しい服を買って着替えようよ。ユウジくんは、どんな服装の女の子が好み?」
そうだなあ、とユウジは返事をしながら、彼女にいちばん似合う服を考えるため、魅力的にディスプレイされた店が立ち並ぶ道を、ゆっくりとハルカの手をひいて歩いていった。


Leave a Reply